X STAR Now
X STARのブログ

X STAR Now

高校や大学、専門学校などの入学金が足りない場合は、早めの対策が必要です。入学後には授業料などの支払いもあるため、まとまった資金を用意しなければなりません。
主な対策としては、奨学金や教育ローンなどの利用が挙げられます。カーリースバックなどを利用する選択肢もありますが、どの方法を選ぶとよいのでしょうか。
本記事では、入学金・授業料が足りないときの対策や、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。これから資金計画を立てる方に向けて、初年度納入金などの目安もご紹介します。

預貯金を取り崩しても大学などの入学金が足りない場合は、外部から資金を調達する必要があります。さまざまな選択肢がありますが、方法によって調達できる資金や準備期間は変わるため、状況に合った手段を選ぶことが重要です。
以下では、入学金が足りないとき・払えないときの主な対策をまとめました。
| 対処法 | 調達できる資金の目安 | 調達にかかる期間 |
|---|---|---|
| 減免や延納の相談 | 資金調達はできない | 1週間~2週間程度 |
| 国の教育ローン | 数十万円~450万円 | 2週間~3週間程度 |
| 銀行の教育ローン | 数十万円~数百万円 | 最短即日~2週間程度 |
| 国や自治体の支援制度 | 数万円~数百万円 | 数週間~1ヵ月程度 |
| カードローン | 年収の3分の1まで | 最短即日~数日程度 |
| カーリースバック | 最大500万円程度 | 数日~1週間程度 |
ここからは、各対策のメリットやデメリット、利用時の注意点などをご紹介します。
各学校の学生支援課などに相談すると、入学金の減免や延納(徴収猶予)に対応してもらえる可能性があります。学業成績が優秀でなくても、結果通知までの間は支払いが猶予されるケースもあるので、まずは減免制度・延納制度の利用を考えましょう。
学校によって手続きは異なりますが、基本的にはやむを得ない理由と、住民票や所得証明などの添付書類が必要です。また、各学校が定める期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請することはできません。事前に手続きを調べた上で、早めの準備を心がけましょう。
| 減免や延納のメリット | 減免や延納のデメリット |
|---|---|
|
|
国の教育ローンは、日本政策金融公庫が実施している公的な融資制度です。受験前や入学後でも申請可能で、最大450万円の教育資金を借りられます。
※上記のいずれにも該当しない場合、融資上限は350万円まで。
国の教育ローンは民間融資より利息を抑えやすく、2025年9月時点の固定金利は年3.15%です。また、返済期間が最長20年なので、ゆとりをもった返済計画を立てたり、子どもの就職後に返済したりすることもできます。
参考:日本政策金融公庫「教育一般貸付(国の教育ローン)」
| 国の教育ローンのメリット | 国の教育ローンのデメリット |
|---|---|
|
|
銀行や信用金庫の教育ローンは、最短で即日の融資が可能です。国の教育ローンに比べると、利用条件や資金使途の条件も厳しくない場合が多いため、ご家庭によっては利便性が高いかもしれません。
金融機関によっても異なりますが、借入上限は数百万円~1,000万円程度、実質金利は年3~5%が目安になります。変動金利しか選べない銀行もあるため、利用前にはローンの仕組みを確認しておきましょう。
| 銀行の教育ローンのメリット | 銀行の教育ローンのデメリット |
|---|---|
|
|
前述の教育ローン以外にも、国や自治体はさまざまな支援制度を実施しています。
たとえば、日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金や給付奨学金は、大学や専門学校などへの進学を支援する奨学金制度です。世帯年収などの条件はありますが、給付型では最大で年間91万円の支援を受けられます(返還不要)。
参考:JASSO「貸与奨学金(返済必要)」
参考:JASSO「給付奨学金(返済不要)」
また、地域によっては都道府県や市区町村の支援制度も用意されています。たとえば、東京都が実施する「奨学のための給付金事業」は、授業料以外の教育費を支援する制度です。
参考:東京都教育委員会「就学を支援する事業の御案内(奨学金制度)|授業料・入学料・支援制度等|」
なかには、国の教育ローンなどと併用できる制度もあります。ただし、お住まいの地域によって制度の内容や仕組みは変わるため、各自治体の公式サイトで確認しておきましょう。
| 公的支援制度のメリット | 公的支援制度のデメリット |
|---|---|
|
|
銀行などの金融機関は、教育ローン以外の融資も用意しています。
なかでも限度額の範囲内で融資を申し込める「カードローン」は、申請時期や資金使途の自由度が高いローンです。金融機関によっては最短即日の融資に対応しており、限度額を超えなければ繰り返し借り入れることも可能です。
ただし、カードローンは金利が比較的高く、特に消費者金融では年15%以上になることもあります。また、貸金業者のカードローンは総量規制の対象になるため、年収の3分の1を超える融資は受けられません(※)。
(※)総量規制は合計借入金額で判定されるため、複数の貸金業者を利用する場合でも、年収の3分の1を超える融資は受けられない。
参考:日本貸金業協会「お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)【貸金業界の状況】」
| カードローンのメリット | カードローンのデメリット |
|---|---|
|
|
カーリースバックとは、所有している車を売却してからリース契約を結び、リース料を払いながら同じ車に乗り続けられるサービスです。愛車を手放す必要がないため、ライフスタイルを変えずにまとまった資金を調達できます。
また、国の教育ローンや奨学金とは違い、資金使途に制限がかかることはありません。総量規制の対象にも含まれないため、車種や年式によっては年収以上の資金調達が可能です。
そのほか、最短数日で入金される点や、申し込みの時期に制限がないこともカーリースバックの魅力です。
| カーリースバックのメリット | カーリースバックのデメリット |
|---|---|
|
|
カーリースバックに興味がある方には、当社の「クルマネー(Kurumoney)」がおすすめです。クルマネーは個人向けのマイカーリースバックサービスで、必要最低限の手数料(名義変更料や環境性能割税など)でご利用いただけます。
クルマネーの売却額は所有車によって異なりますが、最大では500万円の資金をまとめて調達できます。また、リース期間の終了時には名義がご自身に戻るため(※別途手数料が必要)、中古車店などに売却して再び資金調達をすることも可能です。
ライフプランを柔軟に調整できるように、リース期間中の一括支払いにも対応しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
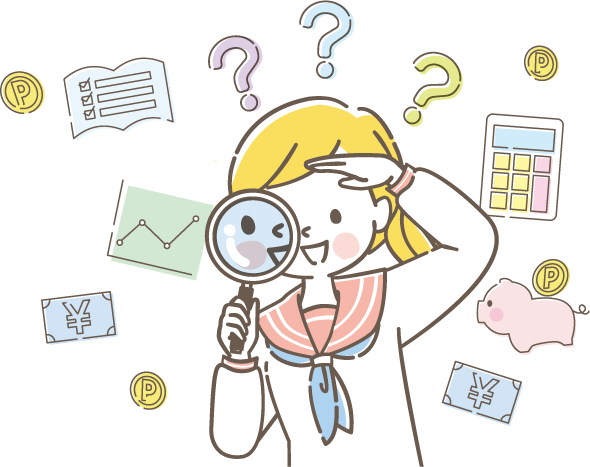
子どもが高校・大学・専門学校に進学すると、実際の学費はどれくらいになるのでしょうか。
以下では、初年度納入金の目安を学校別にまとめました。
| 学校の種別 | 初年度納入金の目安 |
|---|---|
| 公立高校 | 18~25万円 |
| 私立高校 | 50~90万円 |
| 国立大学 | 70~90万円 |
| 公立大学 | 70~100万円 |
| 私立大学 | 110~130万円 |
| 専門学校(理系) | 100~130万円 |
| 専門学校(文系) | 110~160万円 |
※上記の初年度納入金は、全日制または昼間部の平均額を参考にしたものです。
※初年度納入金はあくまで目安で、学部や学科、専門課程などによって変わります。
ここからは高校・大学・専門学校に分けて、初年度納入金の内訳や平均金額をご紹介します。
支援制度などを利用しない場合、公立高校の初年度納入金は18~25万円、私立高校では50~90万円程度になると予想されます。以下の表は、通学関係費等も含めた学費の平均金額をまとめたものです。
| 初年度納入金の内訳 | 公立高校(全日制) | 私立高校(全日制) |
|---|---|---|
| 入学金等 | 1万8,062円 | 7万9,056円 |
| 授業料 | 4万5,194円 | 23万3,102円 |
| 修学旅行費等 | 3万6,452円 | 5万9,293円 |
| 学校納付金等 | 3万5,635円 | 11万2,256円 |
| 図書・学用品・実習材料費等 | 6万2,292円 | 7万4,565円 |
| 教科外活動費 | 4万9,371円 | 5万6,800円 |
| 通学関係費 | 9万7,738円 | 14万2,670円 |
| その他 | 6,708円 | 8,748円 |
| 合計金額 | 35万1,452円 | 76万6,490円 |
※上記の金額は、全学年の学費を平均したものです。
※参考:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します」
上記に学校外活動費は含まれないため、子どもが部活動や習い事をしている場合は、さらに多くの学費がかかります。
文部科学省の調査などによると、大学の初年度納入金は以下の通りです。
※国立大学は法令で定めている標準額です。
※公立大学は2024年度の平均金額です。
※私立大学は2023年度入学者の平均金額で、施設設備費などは含めていません。
参考:e-Gov 法令検索「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
参考:文部科学省「学生納付金調査結果」
参考:文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
学部や学科によっては、実験実習費などが必要になることもあります。また、自宅からの距離や交通手段、一人暮らしをするかどうかによっても費用が変わるため、事前に必要な資金をシミュレーションしておきましょう。
専門学校の初年度納入金(2024年度)は、昼間部で約130万円、夜間部では約101万円が平均になります。ただし、専門課程の分野によって入学金・授業料は異なるため、進学先の情報を事前に確認することが重要です。
参考として、以下では主な専門課程の平均学費をまとめました。
※上記はいずれも昼間部の平均学費。
参考:東京都専修学校各種学校協会「令和6年度 専修学校各種学校 調査統計資料〈概要版〉」
専門課程や学科区分が同じでも、進学先によって学費が大きく変わることもあるので注意してください。

入学金を期限までに支払えない場合は、入学辞退として扱われます。また、授業料の滞納は除籍処分になる可能性があり、一定期間を過ぎると復籍が認められないこともあります。
実習費や設備費などについても、基本的には同様です。学校側が定めた学費を支払わずに、そのまま通学をすることは認められません。
卒業まで学費の支払いを続けるには、事前に「総額でいくらかかるのか?」を確認し、まとまった資金を用意することが必要です。奨学金やローンだけで対応できない場合は、カーリースバックなどの利用も考えましょう。

入学金や授業料が足りない世帯でも、奨学金などを利用すれば進学できる可能性があります。ひとつの対処法で不安な方は、複数の方法を組み合わせることも考えてみましょう。
本記事でご紹介したカーリースバックは、奨学金や教育ローンとの併用も可能です。総量規制の対象にも含まれないため、消費者金融のカードローンなどを利用している方も、お気軽にご相談ください。